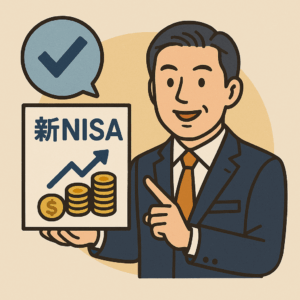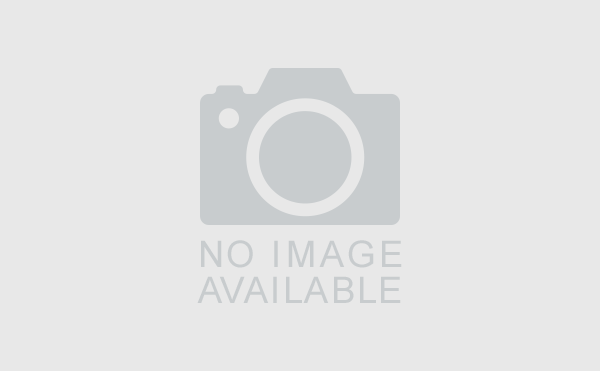iDeCo、賢く老後資金を準備するワケ
「社長の経済学」、今回は、先日ご紹介した新NISAと同じくらい、皆さんの老後資金の準備に大きく関わってくる「iDeCo(イデコ)」についてお話ししたいと思います。「なんだか難しそう…」「自分には関係ないかな?」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。私はiDeCoを5年間ほど積み立てを続けていて、それなりに資産の増加や節税メリットを実感しています。
日頃から不動産市場だけでなく、世の中の経済の動きには常に目を向けるようにしています。そんな中、老後資金の準備については、本当に皆さんにとって喫緊の課題だと感じています。iDeCoは、その対策の一つとしてまた単に節税メリットとしても非常に有効な手段だと考えているので、難しい言葉は抜きにして、できるだけシンプルに、その仕組みから積立てるポイントまでお話ししたいと思います。
iDeCoは重要視されています
皆さんもご存じの通り、日本の少子高齢化は進む一方です。それに伴い、将来受け取れる年金がどうなるのか、不安を感じている方も少なくないでしょう。銀行にお金を預けていてもほとんど増えず、物価上昇で実質的な価値が目減りしていく中で、「自分で老後資金を準備する」ことの重要性がますます高まっています。
そんな中で、政府が私たち国民の自助努力を後押しするために用意しているのが、このiDeCoという制度なんです。これは簡単に言うと、「自分で積み立てる年金制度」のようなもので、税金面で非常に大きな優遇措置が設けられているのが特徴です。
私も、このFPの先生にiDeCoのメリットを教えていただいて始めました。地道な積み立てですが、着実に資産が増えていくのを目の当たりにすると、やはり「やっておいてよかった」と心底思いますね。というか「もっともっと早くやっておけばよかった」が本音です。
それでは、このiDeCoが具体的にどんな仕組みで、どんなメリット・デメリットがあるのか、見ていきましょう。
iDeCoの仕組みをざっくり解説!3つの税制優遇がポイント
iDeCoは、私たちが毎月掛金を積み立てて、自分で選んだ商品(投資信託など)で運用し、原則60歳以降に年金または一時金として受け取る「私的年金制度」です。最大の魅力は、その「3つの税制優遇」にあります。
- 掛金が「全額所得控除」になる! これがiDeCoの最大のメリットと言っても過言ではありません。iDeCoに積み立てたお金は、全額が所得税と住民税の計算から差し引かれます。つまり、その分、支払う税金が安くなるんです。例えば、年収500万円の会社員の方が毎月2万円(年間24万円)をiDeCoに拠出したとすると、年間で数万円の節税効果が見込めます。これは毎年受けられるメリットなので、非常に大きいですよね。
- 運用益が「非課税」になる! iDeCoで積み立てたお金は、自分で選んだ投資信託などで運用されます。もし運用によって利益が出た場合、通常はそれに税金がかかりますが、iDeCoの場合は利益がすべて非課税になります。NISAと同じように、お金がお金を生む「複利の力」を最大限に享受できるわけです。
- 受け取る時も「税制優遇」がある! 原則60歳以降に、積み立てたお金を受け取る際にも税金面で優遇措置があります。
- 年金として受け取る場合: 「公的年金等控除」の対象になります。
- 一時金として受け取る場合: 「退職所得控除」の対象になり、大きな控除が受けられます。 このように、積み立てる時、運用する時、そして受け取る時と、3つの段階で税制優遇を受けられるのがiDeCoの最大の強みなんです。
誰でもiDeCoに加入できるの?
基本的には、20歳以上65歳未満で、国民年金に加入している人であれば、原則として誰でも加入できます。会社員の方、自営業の方、公務員の方など、働き方によって毎月の掛金の上限額が異なりますので、ご自身の働き方に合わせて確認が必要です。
iDeCoの「いいところ」と「気をつけたいところ」
iDeCoは非常に魅力的な制度ですが、注意すべき点もあります。
メリット
- 税金が安くなる効果が強力!: 所得控除による節税効果は、新NISAにはないiDeCo独自の強力なメリットです。毎年確実に手元に残るお金が増えるのは嬉しいですよね。
- 運用益が非課税!: 長期運用で得られる利益に税金がかからないため、効率的に資産を増やせます。
- 老後資金を準備できる!: 原則60歳まで引き出せない仕組みなので、途中で使ってしまう心配がなく、確実に老後資金を積み立てられます。これが最大のメリットと言えるかもしれません。
- 金融リテラシーが自然と身につく: 自分で金融商品を選び、運用状況を確認することで、自然と投資や経済に関する知識が身につきます。
デメリット
- 原則60歳まで引き出せない: これがiDeCoの最大のデメリットです。途中で急にお金が必要になっても引き出すことはできません。したがって、無理のない範囲で掛金を設定することが重要です。途中で積み立てをストップすることも可能ですがその場合でも毎月数百円のコストがかかります。
- 元本保証ではない: 投資信託などで運用するため、元本が保証されているわけではありません。市場の状況によっては、積み立てた金額を下回る可能性もあります。現に、最近のトランプ関税の再燃懸念など、世界経済の状況によっては株価が大きく変動することもあります。
- 手数料がかかる: 口座管理手数料や運営管理手数料など、毎月一定の手数料がかかります。
- 自分で運用商品を選ぶ必要がある: どのような商品に投資するかは、自分で決める必要があります。商品選びに迷う方もいるかもしれません。
iDeCoの今後の展開を予想する
iDeCoは、日本政府が国民の自助努力を後押しする重要な柱の一つです。今後も、国民の老後資金不安を解消するために、制度の拡充や利用促進策が講じられる可能性は十分にあります。
例えば、加入対象者の拡大や、掛金上限額の見直しなどが検討されるかもしれません。また、iDeCoと新NISAが連携を強化し、より一体的に個人の資産形成を支援するような動きも出てくる可能性があるかもしれません。
私たちが生きる時代は、かつてのように「銀行に預けておけば安心」という時代ではありません。政府も、個人が自ら資産形成を行う「自己責任」の時代へと舵を切っていると言えるでしょう。iDeCoのような制度は、そのための強力なツールとして、今後ますますその重要性を増していくはずです。
まとめ:iDeCoは「未来への投資」
長々とお話ししましたが、iDeCoは皆さんの老後資金を安心して準備するための、非常に強力な「方法」です。私も5年間続けてみて、今のところは資産が増えていることを実感しています。
ただし、一番大切なのは、「自分のライフプランや、どれくらいまでなら毎月積み立てられるか(無理のない範囲で)」をしっかり理解して、始めることです。そして、途中で慌てて解約することがないよう、「原則60歳まで引き出せない」という性質を十分に理解しておく必要があります。
今回のブログは、iDeCoについて皆さんが考えるきっかけになればという思いで書きました。私自身、このような制度を通じて世の中の風潮や市場が変わっていく話は好きですし、大人の教養として必要最低限の情報は日頃から得るように心がけています。
繰り返しになりますが、このブログはiDeCoへの加入を強制するものでも、特定の金融商品を推奨するものでもありません。最終的なご判断は、ご自身の責任において行ってくださいね。
ご興味をお持ちの方や、もっと詳しく知りたい、具体的にどう始めれば良いか相談したいといったご要望がございましたら、お気軽にお声がけください。私も皆さんと一緒に学び、より良い資産形成のお手伝いができればと思っています。